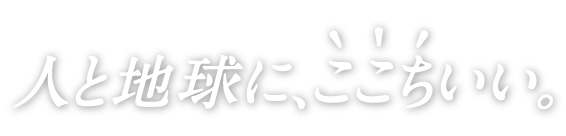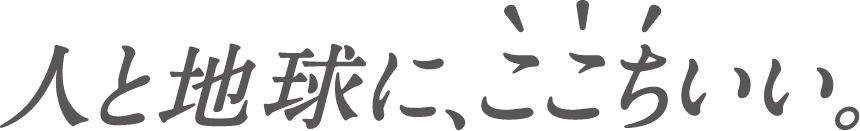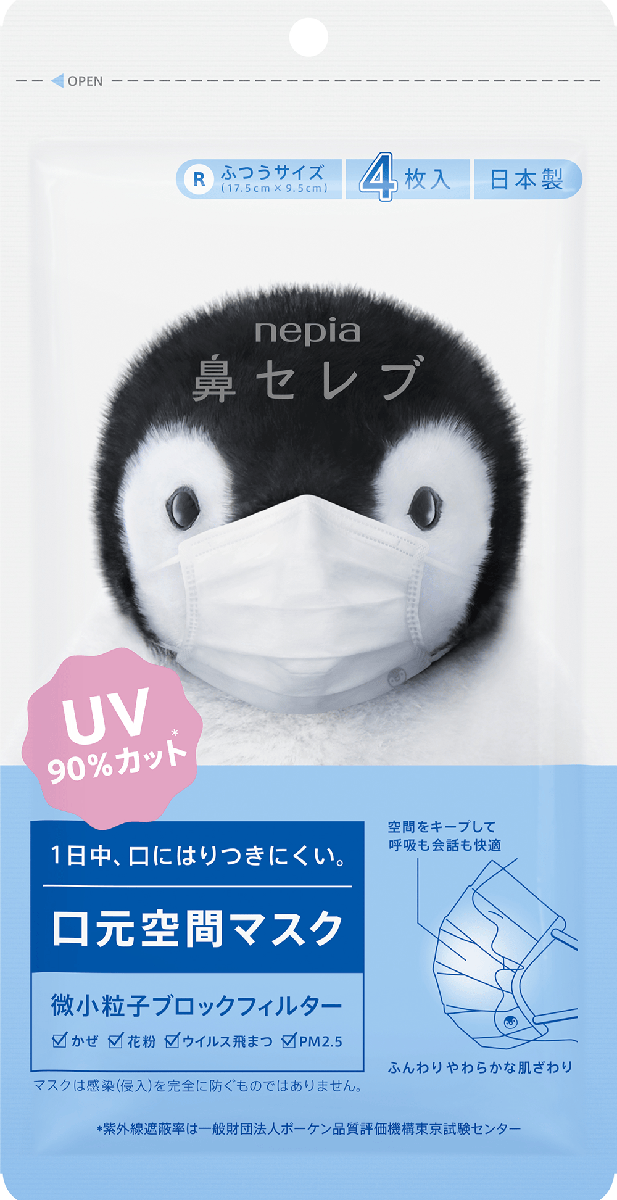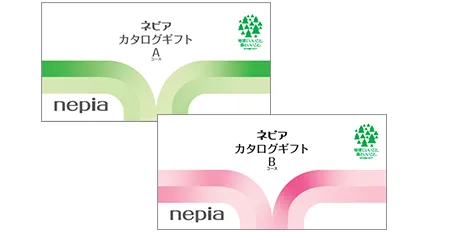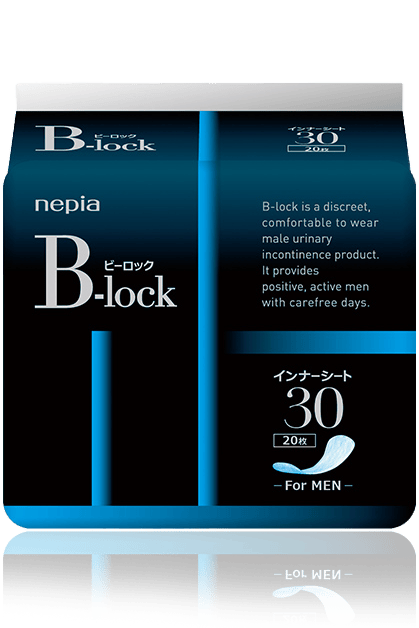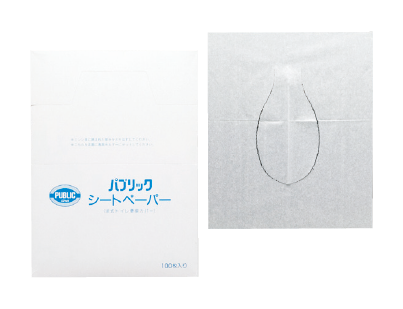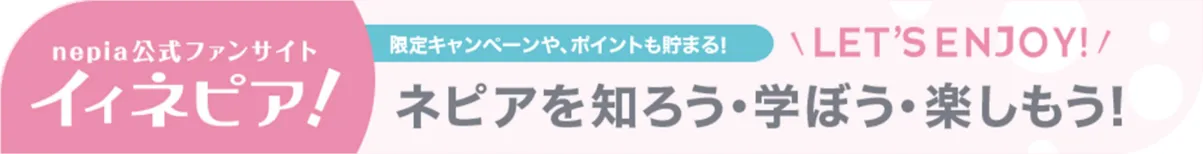Topics
ネピアは、人々の暮らしと環境に寄り添う企業であることを目指し、
「環境価値」と「生活・感性価値」を高める商品開発と価値創造を推進。
「人と地球に、ここちいい。」新しいふだんを追求します。
環境価値
ネピアは、王子グループの一員として、
「森の力」で地球環境を守る
取り組みを行っています。
生活・感性価値
ネピアは、肌ざわりや使い勝手の
さらなる向上に努めます。